« 1960年代にサイケデリック化したアルバムのリリース時期を表にしてみた | 最新のページに戻る | 神経活動の力学系的モデルの初歩 »
■ 「生命の樹」ではなくて「生命の珊瑚」
いまさらだけど、進化について調べている。
「全生命の最後の共通祖先 LUCA (Last Universal Common Ancestor)は地球形成からわずか約3億年後に誕生していた?」という記事を見かけた(2024年7月)。
元論文はこちら: 「[最後の共通祖先]の性質と、それが初期の地球システムへ与えた影響について」 Moody et al. Nat Ecol Evol 8, 1654–1666 (2024).
このLUCAが出現したのは42億年前で、その時期、地球の大気はほとんど二酸化炭素だった。(30~25億年前シアノバクテリアが出現して酸素を作ることで大気中の酸素ができた。つまり、生物が大気環境を変えている。)
だからLUCAも酸素を使わずに、二酸化炭素と水素から酢酸を生成していた、つまり有機物を産出する代謝を行っていたとのこと。そうすると今度はその代謝産物(酢酸)を使う生き物ができる、みたいな生態系を作る余地を生んだ、という推測。
生命の起源がこんな昔に遡るのか、とかいろいろ面白い。
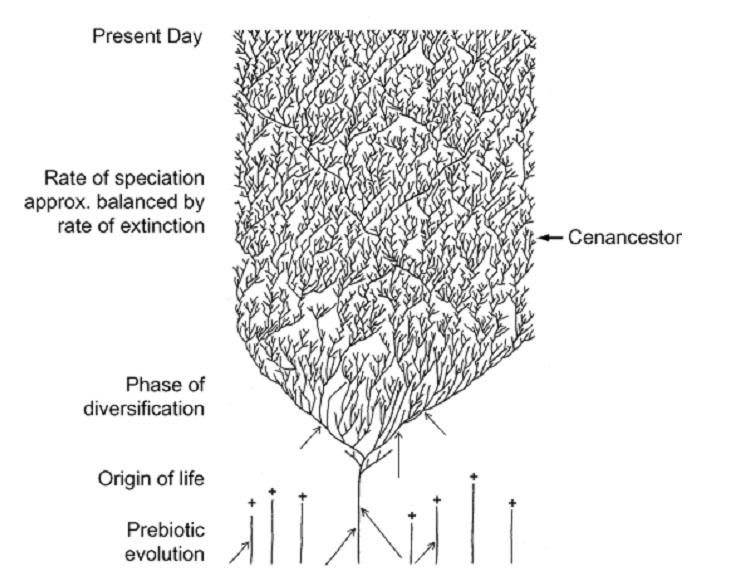
ここでLUCA「最後の」共通祖先とはどういう意味か。ここで絶滅を考慮する必要がある。
ここでJ P Gogartenの総説にあった「生命の樹」(ただし、絶滅した種を含む)を参照しておく。このページで表示しているのはJ P Gogartenのサイトにあるgifファイルだ。
この図でわかったと思うけど、LUCAの「最後の」共通祖先とは、いま生存している生物から見た共通祖先という意味だ。じっさいには現存する生物以外にも絶滅した生物がたくさんいたことを考えると、それら込みでのFUCA「最初の」共通祖先が別にいる可能性もある。そのことがさっきの図だとわかりやすい。(gif動画の中ではLUCAが"cenancestor"と表記されているのに対して、FUCAはもっと下の方に位置している)
2017年の自分のツイートを引用すると、
進化論で出てくる系統樹って、いま生存しているものから遡るんではなくて、絶滅したものまで入れて作れば、たえず枝分かれしては絶滅してゆく繰り返しのなかで、ほんの僅かな偶然を辿っていまここに生存しているというのが見えるはず。 2017年4月10日
さっきのツイートの図を見ると「生存バイアス」を可視化できたようなかんじがしてなんだか面白い。2017年4月10日
あと、この論文を引用している論文を探してゆくと、この図が正確には「生命の樹」というよりは「生命の珊瑚」Corals of Lifeと呼ぶべきであることがわかる。
Wikipediaの"Coral of life"の項にあることをまとめると、
- 「生命の珊瑚」のメタファーはダーウィンがすでに言及していた。
- 「生命の樹」だと、全部が生きているように見える。「生命の珊瑚」なら、いちばん上だけが生きていて、あとはもう死んでる、という事実を反映している。
- 「樹」は枝分かれしかできないけど、「珊瑚」はふたたび合体できる。だから遺伝子の水平伝播も表現できる。水平伝播とは、ミトコンドリアが核に取り込まれたり、葉緑体が植物にとりこまれるとか。
- 種の概念を理解するのに、絶滅種も含めたかたまりを考慮する意義が理解できる。
これは以前からの私の素朴な印象なのだけど、「生命の樹」の根本が太いのはおかしいと思っていた。あそこは細くあるべきなんだよ。せめてその時代ごとの個体数と比例して書くとか。
系統樹に不必要な意味を持たせずに、巨大な家系図なのだと考える*ならばそうあるべきだろう。人類のボトルネック現象**とかもそういう図なら表現できる。
(* これは描かれているのが種なのか個体なのかという問題に関わっている。これは後述の「ナチュラル・ドリフト」の概念につながる。)
(** 19万年前-12万年前の氷期に、まだアフリカから広がる前のホモ・サピエンスが絶滅の危機にあった。日経サイエンス: 祖先はアフリカ南端で生き延びた )
「生命の珊瑚」が生き延びたわれわれの系統だけでなく、絶滅した、まだ化石すら見つからぬ膨大な数の生物の家系図の集合として表現される点に、そして生者と死者をニュートラルに見る視線に、なにか救いを感じる。
進化を「適者生存」として捉える、ネオリベ的というか自己啓発本的な視点がある。あれが元々の進化論には想定されてないことは「理不尽な進化」で指摘されていた。「生命の珊瑚」の図は「適者生存」ではない進化観を持つためにも有効だと思う。
例えばこちらの論文の図1のbとcの違い。図1cのように、生存者を直線にして、絶滅者をそこから枝分かれして消えたものみたいに描くパターンもある。でもそれって生存バイアスに無自覚な行為だ。史学において、勝者の史観を無批判に受け継ぐのと同じ行為だとも言える。
上のツイートでも書いたように、たえず枝分かれしては絶滅してゆく繰り返しのなかで、ほんの僅かな偶然を辿っていまここにわれわれは生存している。勝ってるかどうかなんて、後から懐古的に見ることでしか決定できない*。
生命の珊瑚を現在から遡って推定するという遺伝子解析の手続きだけ見ていると、こういう罠にハマってしまう。あらためて過去から現在へと向かう流れを再構成する視点が必要だと思う。
(* しかも未来いつ絶滅があるかはわからない。ホモ・サピエンスが生存していたのはこの数10万年くらいでしかない。10億年後の地球の生物は、絶滅したホモ・サピエンスの化石を見つけて、かつて反映した三葉虫のように、恐竜のように、ホモ・サピエンスを眺めるだろう。)
長々と話してきたが、生命の珊瑚としての系統樹の見方は、エナクティブな進化観ともよく合致している。「エナクティブな進化観」というのはヴァレラが「知恵の樹」や「身体化する心」で展開した、進化を「ナチュラル・ドリフト」として捉える見方のことを指す。
「ナチュラル・ドリフト」とは、生物が環境と相互的に影響を与え合う関係(カップリング)を維持する(=適応的でありつづける=生態学的ニッチの構築)という構造的カップリングを成立させて、それが系統的に綿々と繋げれてきた軌跡のことだ。このような意味で進化とはナチュラル・ドリフトであり、この視点では種よりも個体の役割が重視される。遺伝子の役割は前面に出てこない。
いま書いている本で、「生命と精神の連続性」という概念に言及しているのだけど、この点を深堀りするならば、やはり進化からは目を背けることはできない。というわけで遅ればせながら、ちょっとずつ読み始めている。そうすると、脳科学でデネット的なものとエナクティブなものが対立するのと同じように、進化でもデネット的なものとエナクティブなものが対立するのが見えてくる。
スタンダードな進化論(デネットとドーキンスを踏まえたもの)の場合は、創造説との対立のほうが大問題なので、デネット的なものとエナクティブなものの対立というのはあまり俎上には上がってこなさそう。(ドーキンス的なものを批判すると、創造説みたいな立場と同一視される恐れすらある)
というわけで要注意な分野なのだが、まあ恐れずに進むのだった。犀の角のように。
- / ツイートする
- / 投稿日: 2025年02月11日
- / カテゴリー: [オートポイエーシス、神経現象学、エナクティヴィズム]
- / Edit(管理者用)